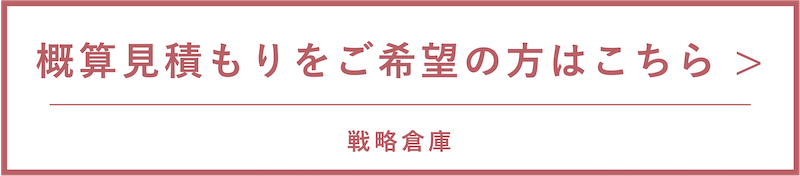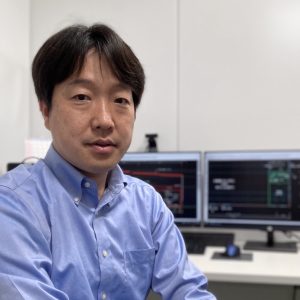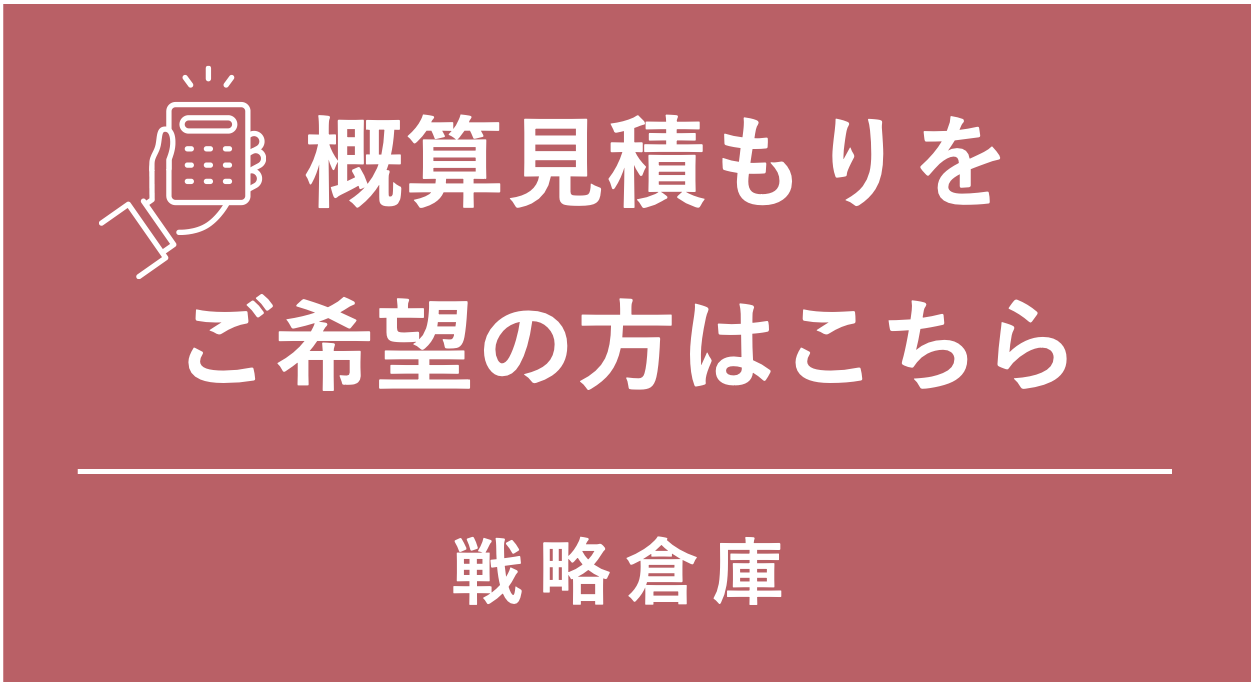ここに目次が入ります
2025.04.05
少量危険物とは何か?定義や取り扱い・保管方法を詳しく解説
こんにちは!北海道〜東北の倉庫・工場の建設会社「戦略倉庫」の久保です。
企業活動において危険物の取り扱いは避けられないケースが多いですが、その中には「少量危険物」という区分があります。
消防法で定められた指定数量未満の危険物には、特有の規制や管理方法があります。
今回のコラムでは、少量危険物の定義や消防法での位置づけ、適切な取り扱い方法や保管時の注意点などを解説します。
企業として安全かつ適法に危険物を管理するための知識を深めていただければ幸いです。

少量危険物とは?定義や消防法を確認!
少量危険物とは、消防法において定められた「危険物」のうち、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を指します。
消防法では、火災発生の危険性が高く、火災が発生した場合に拡大の恐れや消火困難な可能性がある物質を「危険物」として指定しています。
そして、危険物ごとに「指定数量」という数量基準が設けられ、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、消防法に則った適切な取り扱いが求められています。
少量危険物の取り扱いには危険物取扱者の配置は不要ですが、原則として消防署への届け出が必要で、市町村の条例などに基づいた管理が必要です。
例えば、身近な危険物の例だと、灯油は第4類の引火性液体に分類される危険物で、指定数量は1,000Lです。
200L以上1,000L未満の灯油は、少量危険物に該当します。
(※ただし、個人の住宅で取り扱う場合は指定数量の2分の1以上・指定数量未満が少量危険物となります。)
消防法による危険物の分類やそれぞれの指定数量については、こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。
危険物倉庫とは?消防法で定められた建設をする際の基準もご紹介
少量危険物と少量危険物未満の違い
少量危険物未満は、指定数量の5分の1未満の危険物を指します。
少量危険物と少量危険物未満は、両方とも指定数量に満たない危険物ですが、それぞれで規制の内容が異なります。
具体的な違いは以下の通りです。
少量危険物(指定数量の5分の1以上、指定数量未満)
- 消防署への届け出が必要
- 市町村の火災予防条例に基づいた保管設備や管理方法が必要
- 標識や掲示板の設置が必要
少量危険物未満(指定数量の5分の1未満)
- 消防署への届け出は不要
- 消防法や自治体の条例による規制はほぼなし
- ただし、危険物であることに変わりないため適切な管理が必要
少量危険物の取り扱いと保管に関する注意点を解説
少量危険物の取り扱いと保管は、各市町村の火災予防条例によって定められています。
札幌市火災予防条例を参考に、少量危険物の取り扱いと保管に関する基準をご紹介します。
屋外で保管する場合
少量危険物を屋外で保管する場合の主な基準は以下の通りです。
- 保管場所の周囲に容器の種類や数量に応じた幅の空地を確保、または防火上有効な塀を設置
- 液体危険物の取り扱い設備には、流出防止のための囲いや対策を実施
- 地盤面はコンクリートなど浸透しない材料で覆い、適切な傾斜とためますを設置
- 危険物を架台で保管する場合は、不燃材料で堅固に造られた架台を使用
- 見やすい場所に危険物の標識や掲示板を設置
例えば指定数量の2分の1以上の少量危険物をタンクや金属製容器で保管する場合は、周囲に1m以上の空地が必要です。
なお、開口部のない防火構造の壁に面している場合など、一部条件では規制が緩和されることもあります。
屋内で保管する場合
少量危険物を屋内で保管する際には、以下のような基準があります。
- 壁、柱、床、天井を不燃材料で造るか覆う
- 窓や出入口に防火戸を設置
- 液状危険物用の床は浸透防止構造とし、傾斜とためますを設置
- 架台を使用する場合は不燃材料で堅固に造る
- 必要な採光、照明、換気設備を確保
- 可燃性蒸気や微粉が滞留する可能性がある場合は排出設備を設置
これらの基準は火災予防のために設けられたものであり、適切に対応することで安全なリスク管理が可能になります。
異なる危険物を同時に保管する場合の注意点についてはこちらのコラムで詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
危険物の同時貯蔵は可能?危険物倉庫の場合や取り扱いの注意点も解説
少量危険物未満の取り扱い・保管についてもチェック

少量危険物未満の危険物については、消防法や火災予防条例による具体的な規制はありませんが、安全に取り扱い、保管するための基本的な注意点があります。
屋外で保管する場合
少量危険物未満を屋外で保管する際の推奨事項は以下の通りです。
- 直射日光を避け、温度変化の少ない場所を選択
- 防水性のある専用容器を使用
- 直接地面に置かず、台や棚の上に設置
- 地震などに備えた転倒・落下防止対策を実施
これらの対策により、少量危険物未満であっても安全に保管することができます。
屋内で保管する場合
少量危険物未満を屋内で保管する際は、以下の点に注意しましょう。
- 温度上昇しやすい場所は避け、温度が安定した場所を選ぶ
- 日光の影響が少ない場所に保管
- 地震などに備えた転倒・落下防止措置を講じる
- 建物の構造や避難経路を考慮した配置とする
法的な規制が少なくても、危険物の性質を理解し、適切な場所と方法で保管することが事故防止の基本です。
少量危険物とは指定数量1/5以上、指定数量未満の危険物
少量危険物とは、消防法で定められた「危険物」のうち、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の量の危険物を指します。
例えば灯油は指定数量が1,000Lで、200L以上1,000L未満が少量危険物に該当します。
少量危険物は原則として消防署への届け出が必要で、市町村の条例に基づいた管理が求められます。
屋内外での保管には、空地の確保や不燃材料の使用、標識の設置など特定の基準があります。
危険物は量に関わらず適切に管理することで、火災や爆発などの事故リスクを大幅に減らすことができます。
企業として、少量危険物の正しい知識を身につけ、安全かつ法令を遵守した管理を行うことが重要です。
戦略倉庫では、約1,000通りのシミュレーションから最適なプランをご提案することで、低コストで高品質な倉庫や工場を短納期で建築可能です。
倉庫・工場の建築をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。