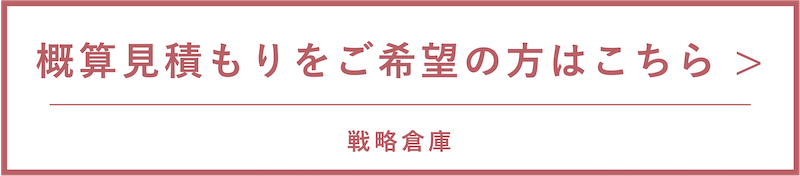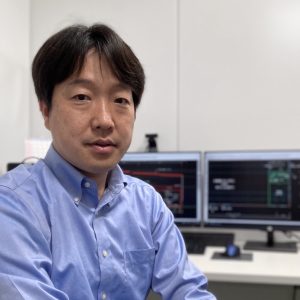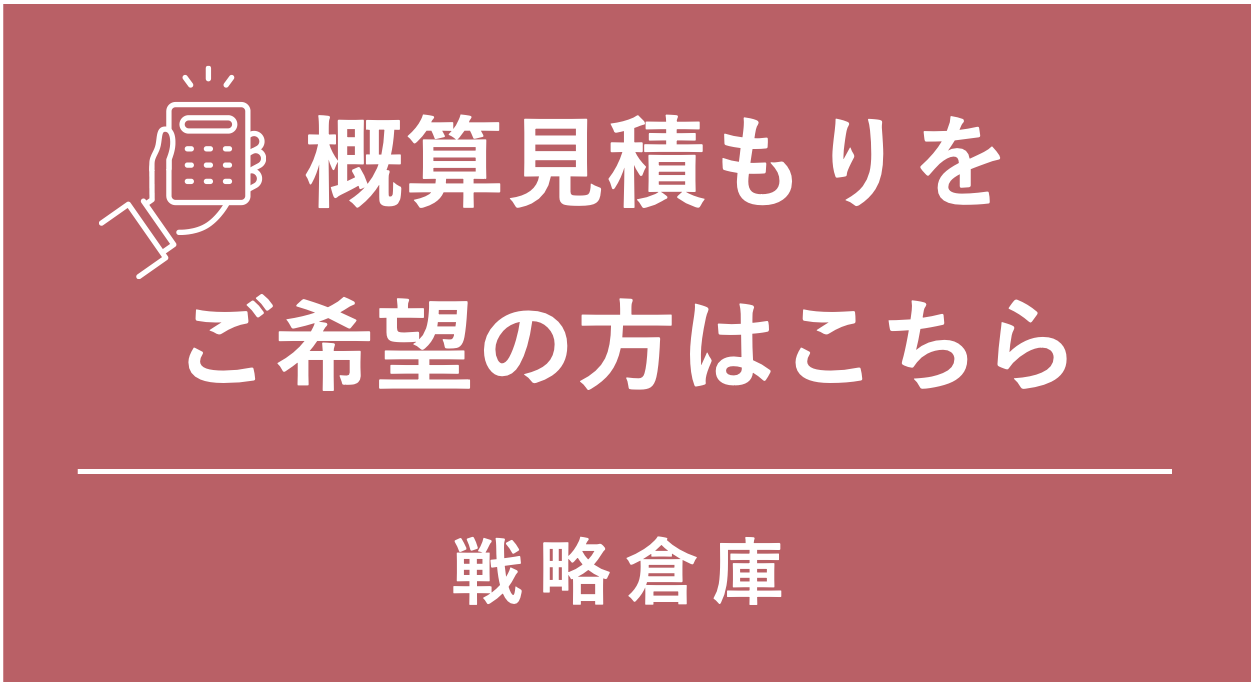ここに目次が入ります
2025.03.10
危険物施設とは?3つの種類や建設基準を詳しく解説!
こんにちは!北海道~東北の倉庫・工場の建設会社「戦略倉庫」の久保です。
工場や倉庫の建設を検討される際、「危険物施設」という言葉を耳にすることがあるのではないでしょうか。
危険物を扱う施設は、通常の建物とは異なる厳しい基準が設けられており、その理解は適切な建設計画のためにも不可欠です。
今回は危険物施設の定義から種類、そして建設時に求められる厳格な基準まで、わかりやすく解説します。

危険物施設とは、どういう施設を指す?
危険物施設とは、消防法に基づいて定められた一定量以上の「危険物」を製造・貯蔵・取り扱うための専用施設のことを指します。
危険物とは、引火性や発火性があり、火災などの災害を引き起こす可能性のある物質の総称です。
消防法第2条第7項では、取り扱いに特に厳格な注意が必要な物質を特徴ごとに6種類に分け、法律上の危険物として指定しています。
危険物がその取扱いに消防法の規制を受ける数量のことを「指定数量」といいます。
指定数量の詳細や種類ごとの基準はこちらのコラムもぜひご覧ください。
危険物施設の3種類について
危険物施設は、消防法で「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3種類に分類されます。
それぞれ危険物の取り扱い目的や方法に応じた役割と、安全を確保するための基準が設けられています。
各施設の特徴と役割について詳しく見ていきましょう。
危険物製造所
危険物製造所は、危険物を製造する目的で設置された施設です。
この施設では1日に指定数量以上の危険物を取り扱うことを前提としており、建築構造や設備、配管などについて消防法により厳しい基準が定められています。
安全性を最優先に考えた設計が特徴で、万一の爆発事故が発生した場合でも被害を最小限に抑える工夫が施されています。
具体的には、爆発の衝撃を効果的に逃がす軽量な不燃材の屋根や、延焼を防ぐコンクリート壁の採用などが挙げられます。
さらに、避雷針、適切な排気設備、十分な照明と採光設備など、さまざまな安全設備の設置も求められています。
危険物貯蔵所
危険物貯蔵所は、指定された量を超える危険物を保管するための専用施設です。
貯蔵所の形態としては、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、各種タンク貯蔵所(屋内・屋外・地下)、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所などが含まれます。
「施設」「貯蔵所」というと建物をイメージするかもしれませんが、移動式のタンクローリーも危険物貯蔵所の一種です。
なお、一般的に「危険物倉庫」と呼ばれるものは、危険物貯蔵所の中の「屋内貯蔵所」を指すことが多いです。
危険物取扱所
危険物取扱所は、製造はしないものの、指定数量を超える危険物を取り扱うための施設です。
危険物貯蔵所との違いは、販売や輸送といったさまざまな目的で危険物を扱うという点です。
具体的な種類としては、給油取扱所(ガソリンスタンド)、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所(ボイラー設備など)があります。
私たちの身近にある施設も含まれており、ガソリンスタンドはその代表例といえます。
また、大規模な商業ビルや施設で見かけるボイラー室なども一般取扱所に分類されます。
身近な場所にも、意外に危険物取扱所が存在していることがわかるでしょう。
危険物施設は基準が厳格!その内容とは

危険物を扱う危険物施設は、「事故発生の予防」と「事故発生時の被害軽減」という2つの観点から、厳格な基準が設けられています。
取り扱う危険物の種類や量によって詳細な要件は異なりますが、ここでは主要な安全基準について解説します。
構造的な基準
危険物施設の構造に関する基準は、火災や爆発といった事故のリスクを軽減し、不測の事態が起きたときの被害を最小化するのを目的に策定されています。
主な構造基準
- 壁・天井:不燃材料を使用し、十分な強度を確保
- 屋根:軽量な金属板などの不燃材料を使用
- 貯蔵容器:適切な強度を持つ材料を使用
- 屋外タンク:防錆対策の実施
特に屋根の設計は重要で、施設内で爆発が起きた際に爆風を逃がし、建物全体の倒壊を防ぐ役割があります。
これらの構造基準は危険物の性質や取扱量に応じて変化しますが、いずれも安全性を第一に考慮したものとなっています。
設備的な基準
危険物施設には、安全確保のための設備の設置が法令で義務付けられています。
主な設備基準
- 避雷設備:指定数量10倍以上の施設への設置
- 蒸気排出設備:可燃性蒸気等が滞留する恐れがある場合に設置
- 採光・照明設備:安全な視界確保のために設置
- 消火設備:施設の規模や取扱危険物に応じた設備を設置
これらの設備要件は取り扱う危険物の種類や量に合わせて定められており、適切に機能することで事故の予防や被害の抑制に貢献します。
例えば、適切な排気システムは有害な蒸気の滞留を防ぎ、十分な照明は作業ミスによる事故を未然に防ぐ効果があります。
配管の基準
危険物施設における配管システムは、危険物の安全な輸送と保管に不可欠な要素です。
配管からの漏洩は重大な事故につながる可能性があるため、高度な安全性能が求められます。
主な配管基準
- 素材・厚さ:危険物の特性に適した強度を持つ材質
- 耐圧検査:配管製造時に十分な水圧試験を実施
- 地上設置:地震や外部環境の変化に対応するための適切な支持構造
- 地下埋設:地盤からの圧力に耐える強度と定期点検が可能な構造
これらの安全規格により、配管からの危険物漏洩リスクを最小限に抑え、長期間にわたる安全な運用が可能となります。
特に地震が頻発する日本においては、自然災害に耐えうる配管システムの強度確保が重要です。
立地や周辺環境の基準
施設の立地や周辺環境に関わる基準は、周辺へ安全確保の視点から極めて重要です。
- 保安距離:施設と周辺の保安対象物との間に一定距離を確保
- 保有空地:施設の周囲に一定規模の空地を確保
これらの規定は、万一の事故発生時に周辺への被害拡大を防止し、消防活動のための十分なスペースを確保するという目的があります。
危険物貯蔵所の基準
危険物貯蔵所、とりわけ一般に危険物倉庫と呼ばれる施設である屋内貯蔵所には、安全性確保のための具体的な基準が設けられています。
これらの基準は施設の規模や構造など、広範囲にわたります。
規模と構造の主な基準
- 軒の高さ:6m未満の平屋建て
- 床面積:1,000㎡以下
- 屋根:軽量な金属板などの不燃材料を使用(天井は原則設けない)
- 壁・柱・床:耐火構造(鉄筋コンクリート造など)
- 梁:不燃材料で構成
- 窓:網入りガラスの使用
- 床:危険物が浸透しない構造とし、「ためます※」等を配置
※「ためます※」=危険物の流出を防止するために設置する容器のこと
爆発時に屋根から圧力を逃がす設計や、危険物の漏洩に備えた床構造など、不測の事態における被害を最小限に抑えるための基準が整備されています。
危険物倉庫の建築基準については、こちらのコラムでも詳しくご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
危険物倉庫とは?消防法で定められた建設をする際の基準もご紹介
危険物倉庫の放爆仕様(放爆構造)とは?必要な火災・防爆対策を解説!
危険物施設とは厳しい基準を満たしている危険物専用の施設
危険物施設は、消防法に基づく危険物を製造・貯蔵・取り扱うための専門施設です。
用途に応じて、危険物製造所、危険物貯蔵所、危険物取扱所の3種類があります。
これらの施設は事故を防ぎ、また、事故発生時の被害を最小限に抑えるため、厳格な安全基準の下で建設・運営されています。
具体的には、爆発の衝撃を緩和するための軽量な屋根構造、火災の拡大を抑制する耐火性の高い壁、危険物の漏洩を防ぐ堅牢な配管システム、周辺地域の保護を目的とした保安距離や保有空地の確保など、多様な安全措置が法令によって求められています。
危険物施設の建設では、これらの規定を正確に理解することが重要です。
戦略倉庫では、約1,000通りのシミュレーションから最適なプランをご提案することで、低コストで高品質な倉庫や工場を短納期で建築可能です。
倉庫・工場の建築をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。