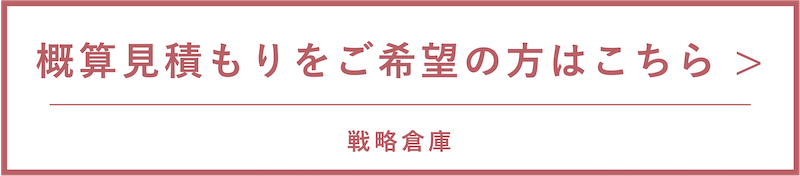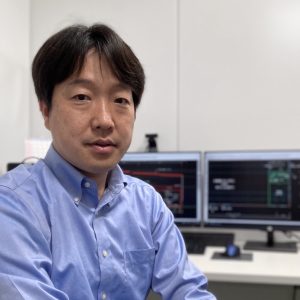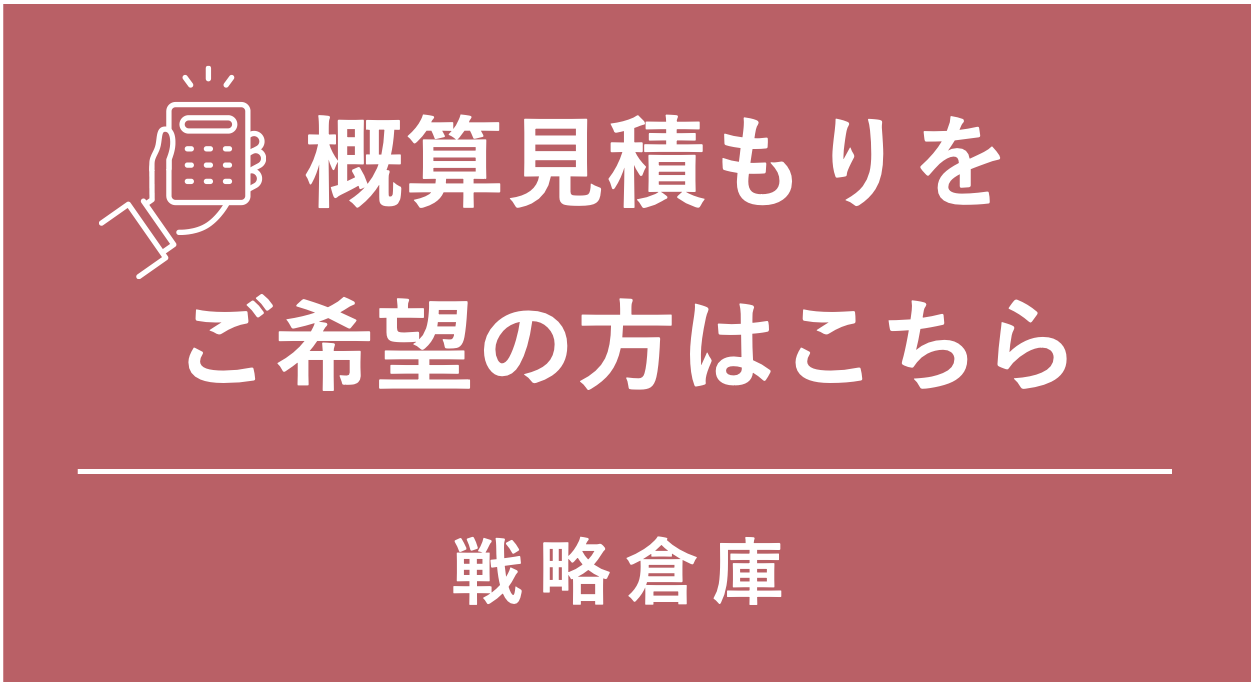ここに目次が入ります
2025.04.12
営業倉庫は危険物倉庫じゃなくても危険物の保管は可能?
こんにちは!北海道〜東北の倉庫・工場の建設会社「戦略倉庫」の久保です。
企業の物流活動において、危険物の保管は特に注意が必要な業務の一つ。
危険物の保管には専用の危険物倉庫が必要というイメージがありますが、実は法改正により条件付きで一般の営業倉庫でも保管できるようになりました。
今回は、営業倉庫における危険物の取扱いに関する法改正の内容や、保管可能な危険物の種類、建設基準など、企業の物流担当者様が知っておくべき重要ポイントを解説します。
危険物の効率的な保管方法をお探しの方は、ぜひ参考にしてください。

法改正で営業倉庫(一類倉庫)でも危険物の扱いが可能に
営業倉庫には、保管する物品の種類に応じて複数の区分が存在します。
主に一般物品を扱う「一類倉庫」、温度管理が必要な「冷蔵倉庫」、そして危険物や高圧ガス専用の「危険物倉庫(危険品倉庫)」などがあります。
以前の倉庫業法施行規則では、消防法で定める危険物は量の多少に関わらず、危険物倉庫での保管が義務付けられていました
しかし、2018年(平成30年)6月29日の倉庫業法施行規則等の改正により、特定条件下では指定数量未満の危険物を営業倉庫(一類倉庫)でも保管できるようになりました。
この改正は、バッテリーやエアゾール製品など、少量の危険物を含む製品の保管ニーズの増加を背景としています。
指定数量とは、消防法で危険物の種類別に定められた基準数量です。
指定数量以上の危険物の保管は、従来通り危険物倉庫での保管が必要となっています。
営業倉庫の種類とそれぞれの倉庫で保管できる物品については、こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。
倉庫の種類はどんなものがある?倉庫別に保管できる物品もご紹介
営業倉庫(一類倉庫)で保管可能な危険物とは?
営業倉庫(一類倉庫)で保管可能な危険物は、次の2つです。
- 消防法第9条の4第1項の指定数量未満の危険物
- 高圧ガス保安法第3条第1項第8号に該当する高圧ガス
消防法では危険物を第1類から第6類までに分類し、それぞれに指定数量が設けられています。
各類の代表的な危険物と指定数量の例を見てみましょう。
- 第1類(酸化性固体):(例)塩素酸カリウム/50kg
- 第2類(可燃性固体):(例)硫黄/100kg
- 第3類(自然発火性・禁水性物質):(例)黄りん/20kg
- 第4類(引火性液体):(例)ガソリン/200L
- 第5類(自己反応性物質):(例)ニトロセルロース/200kg
- 第6類(酸化性液体):(例)過酸化水素/300kg
こういった指定数量未満の危険物、そして高圧ガスで指定された高圧ガスは営業倉庫(一類倉庫)での保管取扱いが可能となりました。
ただし、ここで注意すべき点として、少量危険物の取扱については市町村の条例によって規制があります。
多くの自治体では、「少量危険物」として、貯蔵・取扱いに関する規制を設けているのです。
指定数量未満の危険物なら一律して保管が可能というわけではないため、取り扱い・保管の際には必ず自治体の条例を確認するようにしましょう。
危険物を保管する場合の営業倉庫(一類倉庫)の建設基準は?

指定数量未満の危険物を一類倉庫で保管する場合、一類倉庫としての建設基準に加え、自治体ごとの条例で危険物特有の安全対策が必要となる場合があります。
例えば、札幌市では「札幌市火災予防条例」で、所轄の消防署への届出や、保管施設の技術上の基準が設けられています。
具体的な内容は札幌市の「札幌市火災予防条例【第36条の2(少量危険物の貯蔵等のすべてに共通する技術基準等)】」で確認できます。
営業倉庫(一類倉庫)と危険物倉庫それぞれの基本的な建設基準を確認しておきましょう。
一類倉庫の建設基準
一類倉庫における基本的な建設基準は以下の通りです。
- 建築基準法に適合した構造
- 防犯上有効な構造および設備
- 施錠付きの出入口
- 適切な開口部の保護(鉄格子や特殊ガラスなど)
- 十分な照明設備
- 警備業法に準拠した警備体制 など
危険物保管に関する追加的な基準
危険物を保管する場合は、上記の基準に加えて、自治体の条例により次のような安全措置が必要になることがあります。
- 危険物取扱場所への識別標識・掲示板の設置
- 漏洩・飛散防止機能を持つ設備の導入
- 温度管理が必要な危険物用の温度測定装置設置
- 静電気発生リスクがある場所への除電装置の設置
- 液体危険物保管区画の不浸透床構造と傾斜・貯留設備の整備 など
これらの基準を満たすことで、指定数量未満の危険物であれば、営業倉庫(一類倉庫)での保管が可能となります。
危険物の指定数量や、指定数量以上の危険物を保管する「危険物倉庫」の詳しい建築基準についてはこちらのコラムで詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
危険物倉庫とは?消防法で定められた建設をする際の基準もご紹介
営業倉庫(一類倉庫)で危険物保管は条件次第で可能!
2018年の法改正により、営業倉庫(一類倉庫)でも指定数量未満の危険物の保管が可能となりました。
ただし、通常の一類倉庫の建築基準に加え、少量危険物を保管するための技術基準を満たす必要があります。
また自治体ごとに独自の基準を設けている場合もあるので、自治体の条例を必ず確認してください。
定められた基準や設備を満たすことで、危険物の安全で適切な保管ができるでしょう。
戦略倉庫では、約1,000通りのシミュレーションから最適なプランをご提案することで、低コストで高品質な倉庫や工場を短納期で建築可能です。
倉庫・工場の建築をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。