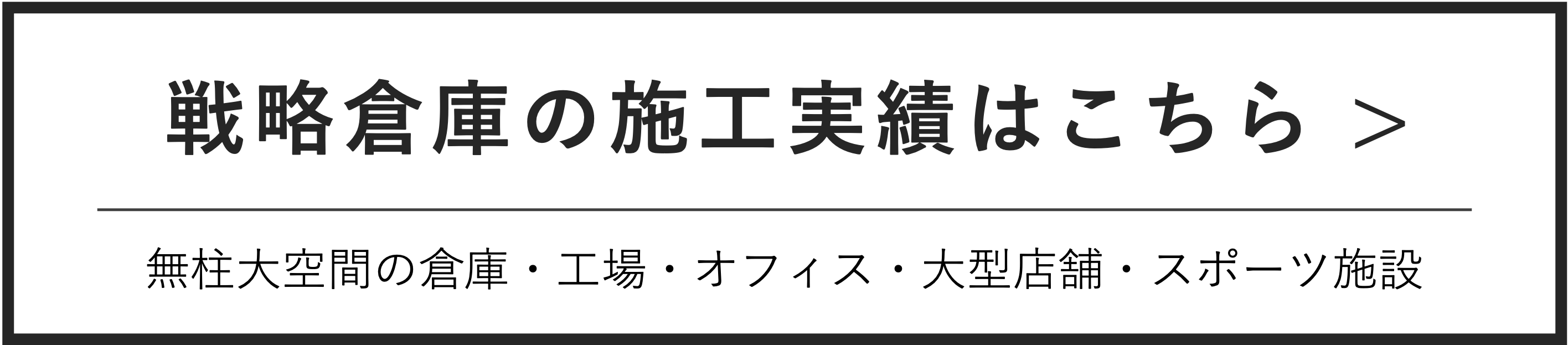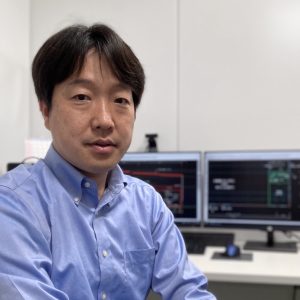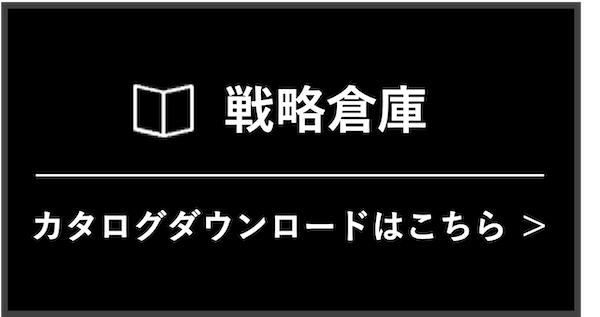ここに目次が入ります
2025.03.26
消防法で定められた危険物の分類とは?安全な取り扱いに必要な基準も解説
こんにちは!北海道〜東北の倉庫・工場の建設会社「戦略倉庫」の久保です。
工場や倉庫で危険物を取り扱う際に「この物質はどの分類に該当するのだろう?」「消防法ではどのような規制があるのか?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
危険物の適切な分類を理解することは、安全な取り扱いと保管のために非常に重要です。
今回のコラムでは、消防法に基づく危険物の分類の詳細や取り扱い方法、また指定数量についてもわかりやすく解説します。

消防法で定められている危険物の定義とは?
危険物とは一般的に、火災、爆発、中毒などを引き起こす危険性のある物質の総称です。
法律の観点からみると、「消防法」上の危険物と「毒物及び劇物取締法」上の危険物があります。
このうち、工場や倉庫での管理により深く関わるのが「消防法」上における危険物です。
消防法上の危険物規制
消防法では、危険物を「火災を発生させる危険性の高い物質」と定義し、特定の物質を消防法上の危険物として指定しています。
これには「火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい物品」や「火災の際の消火の困難性が高い性状を有する物品」も含まれます。
消防法で指定された危険物を指定数量以上取り扱う場合には、市町村等の許可を受けた施設で、政令で定められた技術上の基準に則って行わなければなりません。
危険物を保管する危険物倉庫については「危険物倉庫とは?消防法で定められた建設をする際の基準もご紹介」で詳しく解説しています。
危険物の分類の詳細や取り扱い方法を詳しくご紹介
消防法における危険物は、その性質や特徴によって第1類から第6類までの6つに分類されています。
それぞれの類ごとの特性や安全な取り扱い方法を確認していきましょう。
第1類:酸化性固体
第1類の「酸化性固体」は、反応する相手を酸化させる性質を持っている固体の物質です。
単体では燃焼しませんが、ほかの物質を強酸化させる性質があり、可燃物などと混合すると、熱、衝撃、摩擦によって発火、爆発する危険性があります。
第1類には塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、硝酸アンモニウムなどが含まれます。
【取り扱い方法】
- 酸性物質との接触を防止する
- 可燃性物質と分けて保管する
- 熱源から遠ざけ、衝撃や摩擦を与えない
- 容器の完全性を保ち、内容物の漏洩を防止する
- 涼しく風通しの良い場所で、直射日光を避けて保管する
第2類:可燃性固体
「可燃性固体」は火炎によって着火・引火しやすい固体、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体の物質です。
酸化されやすい物質で酸化性物質と混合・接触すると、発火や爆発の危険があります。
発火しやすく燃焼が速いため、いったん燃えると消火することが非常に困難です。
第2類には硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、アルミニウム粉、マグネシウムなどが含まれます。
【取り扱い方法】
- 酸化剤や空気と接触させない
- 第一類危険物との保管を避ける
- 火気や高温の物体から離して保管する
- 物質に衝撃や摩擦を与えないよう注意する
- 金属粉末類は水との接触は厳禁する
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
「自然発火性物質」は空気にさらされて自然発火しやすい固体や液体、「禁水性物質」は水に触れると発火や可燃性ガスの発生を起こす物質です。
自然発火性と禁水性の両方の性質を持っている物質が多いです。
第3類にはカリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなどが含まれます。
【取り扱い方法】
- 水反応性物質は湿気を厳密に管理した環境で取り扱う
- 自然発火性物質は空気や発火源との接触を制限する
- 保管時は不活性ガス(窒素やアルゴンなど)を封入して貯蔵する
- 液体保存の場合は完全に液中に浸漬させておく
- 小分けにして少量ずつ保管する
第4類:引火性液体
第4類の「引火性液体」とは、文字通り引火しやすい液体です。
可燃性蒸気を発生させ、それが空気と混合したときに火種や静電気、摩擦熱と接触して引火や爆発を起こす危険性があります。
第4類はさらに以下の7種類に分類されます。
- 特殊引火物:発火点100℃以下、または引火点-20℃以下で沸点40℃以下(ジエチルエーテル、二硫化炭素など)
- 第1石油類:引火点21℃未満(ガソリン、ベンゼン、トルエンなど)
- アルコール類:1分子中の炭素の原子数が1個〜3個までの飽和一価アルコール(メチルアルコール、エタノールなど)
- 第2石油類:引火点21℃以上70℃未満(灯油、軽油、キシレンなど)
- 第3石油類:引火点70℃以上200℃未満(重油、クレオソート油、アニリンなど)
- 第4石油類:引火点200℃以上250℃未満(ギヤー油、シリンダー油など)
- 動植物油類:動物の脂肉等または植物の種子や果肉から抽出した物質(ヤシ油、アマニ油など)
【取り扱い方法】
- 厳格な火気使用禁止の措置を取る
- それぞれの引火点以下で保管する
- 第一類及び第五類危険物から隔離する
- 静電気防止対策を実施する
- 液体の熱膨張を考慮し、容器は満タンにしない
第5類:自己反応性物質
熱分解などで自己燃焼しやすい固体や液体の物質です。
燃焼に必要な要素である「可燃物」と「酸素供給体」の両方を含んでおり、比較的低温で多量の発熱を起こし、爆発的に反応が進むという特徴があります。
第5類には有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物などが含まれます。
【取り扱い方法】
- 熱源、衝撃、摩擦を避ける
- 火気を近づけない
- 可燃性物質と分離して保管する
- 直射日光を避け、低温環境で保管する
- 必要最小限の量だけを保管場所に置く
第6類:酸化性液体
「酸化性液体」はそれ自体は燃焼しないものの、可燃物を酸化させることで火災が起こる危険性を持つ液体です。
第六類には過塩素酸、過酸化水素、硝酸などが含まれます。
【取り扱い方法】
- 火気や直射日光を避ける
- 耐腐食性の密閉容器で保管する
- 可燃物や有機物と隔離して保管する
- 物質の特性に応じて水との接触も避ける
- 取り扱い時は適切な保護具を必ず着用する
これらの危険物を安全に管理するためには、適切な設備や構造も必要となります。
危険物倉庫の構造や設備の基準についてはこちらのコラムもぜひご覧ください。
危険物倉庫の放爆仕様(放爆構造)とは?必要な火災・防爆対策を解説!
危険物の分類ごとの指定数量もチェック

指定数量とは、危険物の保管や取り扱いに際して、消防法の適用を受ける基準となる数量のことです。
指定数量以上の危険物の貯蔵・取り扱いには、市町村等の許可を受けた施設で、政令で定めた技術上の基準に従って行わなければなりません。
危険物ごとにそれぞれ数量が定められており、危険物の危険度が高いものほど指定数量は少なく設定されています。
危険物分類ごとの指定数量一覧
各危険物の指定数量は、危険物の規制に関する政令 別表第三で、以下のように定められています。
【第1類:酸化性固体】
- 第1種酸化性固体:50kg
- 第2種酸化性固体:300kg
- 第3種酸化性固体:1,000kg
【第2類:可燃性固体】
- 硫化りん、赤りん、硫黄:100kg
- 鉄粉:500kg
- 第1種可燃性固体:100kg
- 第2種可燃性固体:500kg
- 引火性固体:1,000kg
【第3類:自然発火性物質及び禁水性物質】
- カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム:10kg
- 黄りん:20kg
- 第1種自然発火性物質及び禁水性物質:10kg
- 第2種自然発火性物質及び禁水性物質:50kg
- 第3種自然発火性物質及び禁水性物質:300kg
【第4類:引火性液体】
- 特殊引火物:50リットル
- 第1石油類(非水溶性液体):200リットル
- 第1石油類(水溶性液体):400リットル
- アルコール類:400リットル
- 第2石油類(非水溶性液体):1,000リットル
- 第2石油類(水溶性液体):2,000リットル
- 第3石油類(非水溶性液体):2,000リットル
- 第3石油類(水溶性液体):4,000リットル
- 第4石油類:6,000リットル
- 動植物油類:10,000リットル
【第5類:自己反応性物質】
- 第1種自己反応性物質:10kg
- 第2種自己反応性物質:100kg
【第6類:酸化性液体】
- すべて:300kg
危険物を取り扱う場合には、これらの指定数量を把握し、適切な管理を行うことが法的に求められます。
危険物の指定数量について詳しく知りたい方は、「危険物倉庫の指定数量とは?消防法と建てる際の注意点も解説」をご覧ください。
消防法における危険物の分類取り扱いを理解して安全管理を徹底!
消防法における危険物の分類と指定数量を正しく理解することは、企業の安全管理において非常に重要です。
危険物はその性質に応じて6つの類に分類され、それぞれ特有の危険性と取り扱い方法があります。
各危険物には指定数量が定められており、その量を超える場合には消防法に基づく厳格な管理が必要です。
適切な危険物の分類と管理を行うことで、火災や爆発などの事故のリスクを大幅に軽減することができるでしょう。
戦略倉庫では、約1,000通りのシミュレーションから最適なプランをご提案することで、低コストで高品質な倉庫や工場を短納期で建築可能です。
倉庫・工場の建築をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。